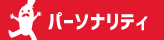今週も、番組をお聴きいただき
ありがとうございました。
今週は、ラジオネーム ひなひな さん からのご相談でした・・・
******************************
中学1年生と、小学校3年生の息子がいます。勉強部屋について伺いたいです。
以前は二人は同じ部屋でしたが、長男が中学に上がってからは、
それぞれ分けました。が、小学校からずっとリビングで宿題などしています。
でも最近、長男の集中力が持たなくなってきたように感じます。
次男の話し声や周りのことにすぐ気を取られてしまい、結局ダラダラと
時間が過ぎるばかり。二人のどちらかに部屋に行くように言いますが、
リビングの方が落ち着くのか、結局二人ともリビングにいます。
私も可能な限りそばで見ていますが、長男は、宿題するのにかなり時間が
かかります。「集中できないなら部屋に行きなさい」と叱るばかり。
息子たちに何と言ってさとせばいいのか・・・。
学習習慣を身につけるには、やはり自分の部屋でさせたほうがいいですよね?
勉強させる環境づくりについても、アドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いします!
******************************
安藤先生からのアドバイスです♪
******************************
中学1年生の息子さんは、去年までは 小学校だったわけですから、
弟さんと同じコミュニティの中で、一緒にリビングで勉強して
っていうところだったとは思いますが、中学生になったことで、
自分だけ難しいことをしていたりとか、自分だけ たくさん やらなくちゃいけない、
様子が変わった、環境が変わった、なんか一人取り残されたかのような
今までとは違う変化があって。
同じように 同じ場所で同じような環境でやっていたという コミュニティから、
自分だけ置いてけぼりになってるかのような、少し自分だけ違ってしまったな
っていうようなところがひょっとするとあるのかもしれませんね。
だからお母さんと弟さんの会話がすごく気になったり、 弟さんが何をしているかが
気になったり、集中が持たなくなってきたってそういう現象が
現れてるの じゃないかな っていう風に思います。
まずはリビングでいる時に、お母様が中学1年生の長男さんに対して、
「小学校の時より中学校になってすごく頑張ってるよね 」っていうこと、
とにかくリビングで勉強していてもそれを認める、そして褒める。
「集中できないなら部屋に行きなさい」 という ネガティブというか
叱るところから行くんじゃなくて、とにかく褒めて認めてやると、
自分も「ちゃんとお母さんは見てくれてるから 孤独じゃない。
ちゃんと認めてくれるから頑張れる。褒められたいからもっとやろう」
なんていう風に子供から大人に変わっていく、今、 境目ですからね。
そういう風にリビングでいても褒めていく、認めていく っていうことをすれば、
今までとは違って一生懸命やるようになると思いますし、
逆に 小学校3年生の弟さんの方が、お兄ちゃんのように自分も頑張ろうかなと、
また頑張り始めると思います 。
今は どちらかというと 弟さんの方の環境によっていく って感じですけども、
お兄ちゃんがもう 脇目もふらず頑張れるようになってくると、
弟さんの方からお兄ちゃんの環境の方に、今度また寄っていくという風に、
いい循環になる可能性もあります。
弟さんにも「ちょっとお兄ちゃんも頑張ってるから、君も一生懸命
お兄ちゃんのように頑張りなさい」 とか「君もできるから頑張ってね」と。
弟さんの方がちょっとストレスかかるかもしれませんが、それはまた別の機会に
フォローするとして、お兄ちゃんを褒めて認めて っていう
そこをまずされていくと良いのではないでしょうか。
さらにその お兄ちゃんの中学校1年生のお勉強に、目標とか目的 っていうのを
親と共有して。
例えば「今度のテストで何点取ろうね」「 順位 何番 取ろうね」 とか、
そういったものに対して、親も子も一生懸命、一緒になってその目標を、
これを頑張って取ろうねっていう、弟にはない長男さんだけのことで
母と長男が盛り上がっていく ってことですよね。
そうするとだんだん頑張ろうっていう 波に乗ってくる。その波に乗せていく、
ということですよね。
その波に乗せていくことを今度やっていくと、長男さんの方から、
「ちょっと部屋で勉強してくるわ」って、自分から言ってくると思います。
「行きなさい」って言って部屋に行く勉強は、やっぱりリビングのことが
気になります。
だから申し上げたようなステップを踏むことで、最終的には自分から、
「ちょっと部屋で勉強してくるよ」 っていうことを言い始めると思います。
そうなってくるとだんだん 本当に自立していくということに
つながっていくんじゃないかな、 そういう風に思います。
******************************
安藤先生へのご相談は
メールフォームから お気軽にお寄せくださいね!
その後のエピソードなども
お待ちしています!