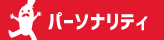今週も、番組をお聴きいただき
ありがとうございました。
今週は、匿名希望 二人の子どものママです さん からのご相談でした・・・
******************************
最近、下の子(息子2歳)の主張が強くなり、言うことに反発したり、
いたずらに度が過ぎると、思わず頭をはたいたり、手を出してしまいます。
私も小さい頃、母親に手を出されていたので、
自分はしないようにしようと思ったのに、いつも自己嫌悪に陥ります。
どう自分をコントロールしていけばいいのかわかりません。
上の娘から、「怒ったらあかん」と言われたときはショックでした。
娘は私の表情をうかがうようになり、我慢させてしまうことがあります。
私もそうでした。怒る顔を見るのが嫌で母親の表情をうかがっていました。
母親と今でも一線引いている自分がいます。
子どもにはそんな思いはさせたくありません。アドバイスをください。
よろしくお願いします。
******************************
安藤先生からのアドバイスです♪
******************************
つらいですよね。
そのまま言いますと・・・このお母様 ご自身が、自分と自分のお母さん、
かつての関係ですね、今でも一線引いてるってことですが、
実は、この自分とその自分のお母さんとの安心の関係を築きたいっていうところが
一番のところだと思います。
2歳のお子さんがどうこうじゃなくて、自分と自分のお母さんとの関係が
整ってくると、2歳のお子さんも変わっていくと思いますね。
それはどういうことかって言うと、お母さんに、小さい時どうしても
顔色を伺って怖かったとか色々あったということですけれども
その頃の思いを伝えるって事です。
自分はその時に それを伝えたかった。本当はこういうことが言いたかった。
だけど怒らせてしまうとダメだと思って 我慢をしてきた。
だけど 本当はこう思っていたと伝える、これがひとつです。
とはいえ そういうことがあったから、今の自分があるんだと、
なかなか色々つらかったことあったけど、だからこそ今の自分があるんだ
っていうことですね。そこに意識を向ける。 これが2つ目ですね。
3つ目は、
その頃の自分を癒してあげるということです。
あの頃の自分だと思って、たとえば、枕をぎゅーっと抱きしめるんですね。
「つらかったよね 我慢したよね 必死だったよね わかるよ」と、
あの頃の自分を癒せるのは今の自分だけです。
こういう風なことをしていくと、自分と自分のお母様との関係が
少し変わったりします。
そうすると 息子さんの状況も少し変わってきたりします。
もっと言うと、そんな自分と自分のお母さんとの関係を良くしていくために、
サポートしてくれるために、 2歳の息子さんはこのように導いてくれてるのかも
しれない。
あの頃 小さかった頃、自分のお母さんに本当は言いたかった、やりたかったことを、
2歳の息子さんが今見せてくれてるのかもわからないですね。
だから自分も一度、お母さんに どういうことを言いたかったんだろうかと
思い出して伝えてはいかがでしょう。
そして あれがあったから今があるんだということにも意識を向ける。
自分で あの頃の自分を癒してあげる。そういうことですね。
2歳のお子さんがいたずらに 度が過ぎたりねすると、やはり
その目の前の状況なんとかしないとだめですから、
どうしても思わず頭を働たたいたり手を出してしまったり、
それはいいことかって言うと あまりいいことじゃないかもしれません。
けれども、手を出してるのはいったん横に置いといたとしても
中長期的に長く大きな目で見ると、昔々、お母様が小さい頃
どうしたかったかっていう、あの頃の本音を、
2歳の息子さんは、こうしたかったんじゃないの っていうぐらい、
実は見せてくれてるのかもしれませんし、
一方で、時に我慢していた自分っていうのを、
お嬢さんがですね 見せてくれてるのかもしれません。
我慢して頑張ってきたから、お嬢さんから「怒ったらあかん」と言われたのは、
かつての自分が言ってるような気がして ショックだったのかもしれません。
「また 我慢しなくちゃいけないのか、自分だって我慢しながら どう言えばいいか
わからなくて。でもそれを出したらこうなるし、でも我慢したらこうなるし」と。
今回、メールの中での解釈なので、詳細は分かりませんが、
今回のことは、息子さんもお嬢さんも、お母さんのことをとても愛していて
とても大切に思っていて、だからこそ お母さんに
一つ一つ楽になってもらいたい。お母さんにも幸せになってもらいたい。
そういう気持ちを 無意識に見せてくれてるのだな っていうことを感謝して、
自分のあり方を見つめてみることも大切 なんじゃないかな っていう風に思いました。
******************************
安藤先生へのご相談は
メールフォームから お気軽にお寄せくださいね!