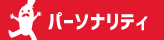今週も、番組をお聴きいただき
ありがとうございました。
今週は、ラジオネーム あすか さん からのご相談でした・・・
******************************
小学校5年生になる息子のことですが・・・
授業のノートがグチャグチャで、
どこに何が書いてあるのか、本人ですらわかっていないようです。
筆圧も弱いです。
これから授業の難易度が上がっていくと、壁にぶつかりそうで・・・。
何度も「丁寧に書こうね、消すときはきちんと消そうね」と言いますが
気にしていないようで改善が難しいです。
少なくとももう少し丁寧に書くことを意識させるのが大事だと思うのですが、
何かいいアドバイスはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
******************************
安藤先生からのアドバイスです♪
******************************
2点あります。
まず、「丁寧に書こうね 消す時はきちんと 消そうね」って本人にそのように言って
そして改善がされる かっていうと、なかなか難しいです。
理由は、
どうして 筆圧が弱く 薄く書くのか、どうして 丁寧に書かないのか、
どうして消す時にきちんと 消さないのか・・・その理由が 本人の中にあるんですね。
例えば、もっと幼い頃に「早く書きなさい」ということをすごく言われたから
早く書かないとだめだとか、
すぐに消そうとしたら「すぐに 消しちゃダメ」って言われたとか。
そこまで本人が遡れるかどうか分かりません。けれども、
目の前に見えた現象だけを捉えて「だめです 直しなさい」って言っても、
本人にはその現象を引き起こしてる理由があるんです。気持ちがあるんですね。
その理由 やその気持ちは 何かわからないですけど、
一旦 そこに寄り添ってあげるって事が大事ですね。
それは問い詰めるんじゃなくて、「何で消さないの?」って聞いてあげることです。
そして、「そうなんだ」と受け止めることです。
次に、それをしないとどう困るのか っていうことですね。
お母さんはこういうふうに困るとつたえます。
本人は本人の中に正義があって、「何も悪くない 自分はこれでいい」と
思ってるかもしれませんけど、ゆくゆく それだとどう 困るのか っていうのが言えるなら、
お母さんが 息子さんにそこをゆっくりと話してあげることです。
そして、「一緒にやる」って事です。
「じゃあ 書いてみようか」と、一緒に書いてみるということですね。
「ちゃんと書きなさい」じゃなくて、「一緒にちゃんと書いてみようか」って一緒にやるって事です。
それも、一緒にやる時には、暖かい空気の中で、笑顔で、一緒にやるって事です。
人は感情の生き物なので、どれだけ正しいことでも その時の空気が嫌だったり
なんかつまらなかったりすると、どれだけ正しくってもやりたくないですよね。
その時の空気が暖かくて明るくて笑顔があれば、「じゃあやってみようかな」
そう思うわけなので、言って直すというよりも、一緒にやって直す。
そこには笑顔があって、一緒にいる、それから 直す。
もし、慌てて 早く書かないとダメだとか、そうしないとみんなに置いていかれるとか、
かつて置いていかれた時の悲しみがあったりとか、
筆圧を濃く書いたことによって、周りが汚れてしまったりとか手が汚れてしまったりとか、
それを誰かに言われたとか・・・
かつて 自分はそれで 悲しい思いをしたとか、そういうのがあれば
「そうなんだね」と、1回 寄り添ってあげることです。
「自分なりに頑張ったんよね。頑張ったけど たまたまそうやったんよね。
それはそれでわかるよ。だけどそれは 悪いことじゃないし。
ただ、お母さんが思うのは、きっちり書いた方が後が見やすいかなって思うわけだけど、
あとは自分が決めて行きなさい 」とかね。
片一方が片一方を強制するとか、力づくで直すとか、そういうことじゃなくて、
寄り添いながら話をすることが大事ですね。
ゆっくり書きすぎたらみんなに置いてかれたとか、だから早く 書かないとダメだとか、
本人なりに、生きていくために一生懸命 必死にやっていることかもしれません。
だから まずは 本人なりにそうやっていることを肯定した上で、
一緒にやっていくのです。
もう1つは、
全く これは 字のこととは離れますけれども、
丁寧に書かない きちんと 消さないっていうのは、生活の中で、
例えば、ご飯食べた後 椅子を引かないとか、トイレの電気をきちんと 消さないとか、
一個一個のめりはりが、勢いでメリハリなく流れて行ってしまってるっていう事も
ひょっとするとあるかもしれませんね。
その時の体の姿勢、箸の持ち方、 電気はつけたら電気は消す、
「丁寧に暮らす」っていうことと「丁寧に書く」ということは 繋がります。
だから、「丁寧に暮らす」っていうところからのアプローチも
大切なんじゃないかなと思います。
******************************
安藤先生へのご相談は
メールフォームから お気軽にお寄せくださいね!