今日は昨日に比べると少し寒い一日でしたよね。
気温の変化が大きい季節の変わり目
体調管理お気をつけ下さいね!!
さてさて今日のEVENING COASTER・・・
まずはこのコーナー
週替わり月1コーナーTOPIC
第2木曜日は、「SPORTS Journal」
スポーツマネジメントの世界について
鈴鹿国際大学 市野 聖治 教授にお話をうかがっています。
今回は、電話をつないでお話を伺いました。
さて、今回の話題は・・・
「スポーツ・イベントのマネジメント」について
1、スポーツは、文化だと言われている
具体的に、、、
教育、医療、街づくりに貢献したい。
2、スポーツと人の関わり
①スポーツを行う
②スポーツを見る
③スポーツを支える
3、スポーツ・イベント(行事、催しなど)
→人とスポーツの関わりの場
運動会など
4、スポーツ・イベントのマネジメント
・運営による成果
5、名古屋ウィメンズマラソン2013を参考にして・・・
「名古屋ウィメンズマラソン」は、もともとは「名古屋国際女子マラソン」で
女子マラソン代表選考レースを兼ねて実施されていました。
そして、2012年からは、エリート選手のみならず一般市民も参加する
「名古屋ウィメンズマラソン」として開催。
女子マラソンでは世界最大参加 13,114人 ギネス記録にも
2013年は、参加者14,554人と記録を更新。
本当に大きな大会だとかんじますよね~。
そして、この大会にはコンセプトがあって
~すべての女性に笑顔と幸せを~
支援先、ピンくリボン、ホワイトリボン、ガールエフェクト、東日本大震災被災地です。
イベントの大会もやり方によって 大きな 社会貢献になるということです。
この5つのポイントでスポーツ・イベントのマネジメントについてお話いただきました。
春という季節、新たにスポーツを始められる方、
スポーツイベントに参加される方、多くいらっしゃると思います。
また、イベントなども行われる季節です。
ぜひ、積極的にスポーツイベントに参加してみてはいかがでしょうか。
市野教授 ありがとうございました!!
***************
番組後半 18時31分頃にお届けしたのは
来春導入!「津市の小中一貫教育」について。
津市教育委員会 事務局 教育研究支援課 課長
荻原 くるみ さんにスタジオにお越し頂きお話伺いました!

Q まずは、「小中一貫教育」そのものについて
A まず、いわゆる私立の「中高一貫教育」とは異なります。
小学校中学校で教えるべき内容、それを大きく変えるとか、前倒しするということも考えていません。
指導すべき内容は、学習指導要項で定められており、それらをしっかり子供たちに身につけさせるために実施するもの。
Q 日本の教育は、6・3・3・4制というのが広く定着してきました。
一方で、これを見直そうという動きもあるように聞いていますが、
今回の「小中一貫教育」というのは、これに呼応した、あるいは先取りした取り組み?
A 他県では小中学校9年間の6・3制を4・3・2制という区切りにすると
学力の向上が図られた、いわゆる中1ギャップが解消されたという報告がされていますが
津市の小中一貫教育はこういった制度改革を推し進めるものではありません。
小学校と中学校の接続を滑らかにすることで子供たちの学力向上
中1ギャップの解消が図られると期待するものです。
Q 「中1ギャップとは?」
A 一般的に、小学校を卒業し、中学校1年生になると
学習内容や生活リズムになじめず、不登校やさまざまな問題行動が
急増するといった現象のことを言います。
Q 「小中一貫教育」のメリットは?
A 津市ではすでに2つの校区で小中一貫教育モデル校として取組を進めています。
また連携型小中一貫教育を進めている学校区があります。
これらの校区ではすでに学力向上や、社会性の慎重(不登校生徒の減少、問題行動の減少)
といった効果が出ています。
Q 一方、デメリットや課題は・・・
A 複数の小学校から1つの中学校に入学してくるといった実態ですので
互いの授業を見合ったり、行事をともに行ったり
そのための打合せをするための時間の調整や確保が課題です。
Q 具体的には、どういうスケジュールで導入されている予定?
A 4月から中学校区で話し合いをしっかり行い、具体的な部分を決めていきます。
平成26年度には、各中学校区のスタイルでスタートが切れるようにしたいと考えています。
Q 学区や校舎、先生、カリキュラムなどはどうなる??
A 学校の通学区域とかこれまでの校舎が大きく変わるということはありません。
小学校と中学校の先生方の教育に対する共通理解がすすみ、
子どもたちが中学校に入学する際の不安感をできるだけ減らしたり
学習意欲をあげたりしようとするものです。
お話いただいた、一部分を書かせて頂きましたが・・・
今回、初めて聞いた、知ったという方もいらっしゃるかもしれません。
保護者の方への説明などはこれからしっかりと行い
周知のための方法も考えて行きたいとおっしゃっていらっしゃいました。
お忙しい中、スタジオにお越しいただきました。
おぎはら さん。ありがとうございました!!
***************
ではでは今日はこの辺で!!
また来週月曜日。よろしくお願いします☆☆




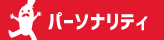


 メッセージ&リクエスト
メッセージ&リクエスト